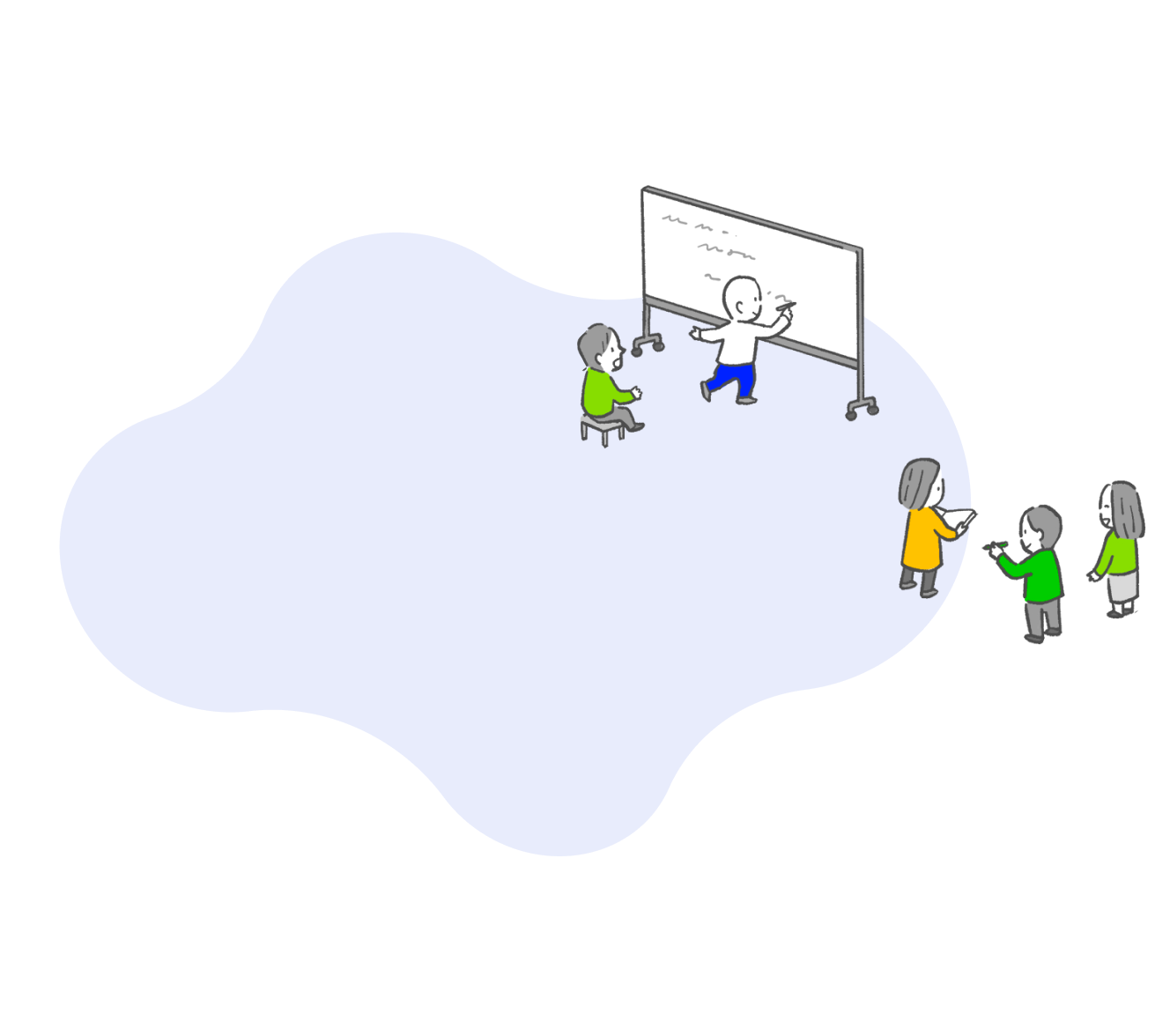4/26(土)にGoogle meetを用いたオンライン形式で
「1・2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」
~面接実践編・オリジナルコース~
を開催いたしました。
こんにちは。働く楽しさ研究所・八阪です。
先日の『面接準備編』と『面接お手本編』の講座を経て、
この日は参加者の方がロールプレイをされる『面接実践編』を
今シーズンで初めて開催いたしました。
久々にチャットでのリアルタイムフィードバックをすることもあって、
ちょっと緊張もしながら、そして操作感覚も思い出しながらの講座運営になりました。
ZoomからGoogle meetに切り替えたこともあって、
ちょっとドタバタしましたが、大きな事故もなく、無事に開催できてよかったです。
この『面接実践編』はロールプレイが経験できることもあって、
毎回大変多くの方に来ていただいています。
今回はまだ4月ということで、試験本番までは日数がある時期ですが、
この段階ですでに実践練習に取り組もうという意欲の高い方が来てくださいました。
今シーズンから初めて弊社の講座に来た方も、
リアルタイムでどんどんチャットで指導が入っていく様子が
見ていて新鮮で面白かったのではないでしょうか。
また、何を書いているかという内容だけでなく
関係構築や問題把握のポイントになる箇所への”目を付ける速さ”だったり、
“視野の広さ・思考の深さ”などもいい学びになったかと思います。
中には、ロールプレイ自体に慣れていない中で、
勇気をだして参加してくださった方もおられましたね。
その姿勢への拍手をお送りするとともに、
講座の中でお話した、熟練レベル・指導レベルに到達するための
技術とマインドの両方についてお話しましたので、
ぜひこれからも、ご自身の力を磨いていってほしいです。
今回も、stand.fmの音声配信形式での振り返りを収録しました。
この記事にもリンクを張って紹介していますので、
振り返り講座に参加された方はもちろん、この記事をご覧になられたみなさんに
ぜひ上手に活用していただければ嬉しいです。
「1級 面接実践編・オリジナルコース」の振り返り
「2級 面接実践編・オリジナルコース」の振り返り
では、ここからは、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。
今回も受講された方の意欲や熱意が伝わるメッセージが届いています。
このアンケートへの取り組み方1つとっても、その人の学びに対する意欲や本気度が
伝わってくるのではないでしょうか。
技能士試験の合格を目指すなら、自分の言葉でアウトプットすることへの
質・量へのこだわりは、ぜひ持っていて欲しいですね。
この記事を読んでいるみなさんも、本気で合格を目指す方のアウトプットの質を
ぜひ感じ取っていただけると嬉しいです。
1・2級 面接実践編・オリジナルコース 参加者の声
今回は、勇気ある皆様のロールプレイを見学させていただき、ありがとうございました。
特に印象に残ったのは、1ケース目の「笑って話せることではないのに、相談者はなぜ笑いながら話しているのか?」というお話です。八阪先生の「あなたはいつもそうやって辛抱してるんですか?」という一言は、衝撃的でした。その一言で、相談者の日常の様子をありありと思い描かれていることが体感的にも伝わってきたからです。どうすれば相談者に安心してもらえるのか、「来てよかった」と思ってもらえるのか。今回の講座を通して、面談においても、人と人との関係性と根っこの部分は変わらないことがより深く感じとれました。
過去の自分を振り返ると、面談とプライベートは別モードと考えていたのかもしれません。八阪先生の講座を通して、日常会話ベースで意識して振り返るようになってから、変化を感じられています。
たとえば、最近、職場の後輩に対して「こういう場面では自分から提案した方が良いと思う」と言ってしまった出来事がありました。受講後に自分自身を振り返った後、自分の説明や後輩の話を聴く姿勢が足りていなかったこと、そして後輩がこの職場で働けてよかったと思えるように自分自身で考えて行動できる力を身につけてもらいたかったことをお伝えしました。すると、涙ぐんだ様子で背景にあった事情や悩み事をお話ししてもらえたり、その後は後輩自身のアウトプットの質も高まったように感じられたりしました。
ただ、こうした目に見える変化もある一方で、自分基準で発してしまった言葉にも気づきやすくなり、今までの考えがいかに甘かったか、自分自身の至らなさを感じる機会も増えました。でも、気づけるようになったことが第一歩で、気づけない状況の方がよほどまずいと思えることは、進化の証だと捉えています。自分の至らなさと向き合うのは苦しいこともありますが、努力したいと思えるものがある状態は楽しいことだと、感じられるようになった今が嬉しいです。
今後は、相手第一を実践できるようになるために、説明にすぎない内容ではなく「相手がわかってほしいこと」に注力できる余白をつくるよう、日常の中で意識して練習します。八阪先生の「聴くことの90%は考えること」という一言が、今後の自分自身の課題のヒントになりました。今回も貴重な学びの機会をいただき、本当にありがとうございました。
初めて参加させていただきました。目からウロコの講座で多くの気づきと学びがありました。大変貴重な時間をいただき感謝いたします。講座での学びを活かし、今後は下記3点に取り組みたいと思います。
①CLに主導権をお渡しし、CLがお話したいことから自由に話せる場づくりを意識します。
今までは主訴を引き出すために、どんな質問をしたら有効だろうか?ということに捕らわれていたことを痛感しました。今後は、試験だから…時間配分をして具体的展開まで進めなければ…という意識を持たずに取り組みます。CL第一で、どうすればCLが元気になるのか?CLを分かろうとする姿勢を大切に臨みたいです。
②CLからのNOや沈黙を恐れずに対話をします。YESだけが正解ではないという言葉が印象に残りました。NOを言っても聞いてくれるCCだと思っていただけるよう、丁寧に関係構築を行いたいと思います。
③当事者意識を持ち参加します。集中して講座に参加することはできましたが、貴重な質問タイムに質問をすることができませんでした。自分だったらどうか?という当事者視点が不足していたことが反省点です
日常から他者との関わりのなかで意識をして取り組み、試験に向け準備をしていきたいと思います。今後ともご指導いただけると幸いです。
これまで3回受検して実技面接(具体的展開)の点数が足りず合格できないでいます。
1回目・2回目とも時間内に目標と方策の合意まで至らなかったことから「タイムマネジメントを改善する必要がある」と考え、20分以内に少なくとも目標の共有まで辿り着くことに血道をあげて練習してきました。ところが3回目でも具体的展開が未達に終わったばかりでなく、問題把握まで合格点ながらも点数を下げてしまう始末で、どうしたものかと悩んでいました。
今回、面接実践編を見学者として受講し、タイムマネジメント改善とか目標共有に辿り着けるとかではなく、そもそもCC視点の問題把握ができていない、もっと言うと相談者の主訴すら実は掴めていなかったことを思い知りました。評価区分や試験範囲の細目も読み込んではいましたが、表面的な理解しかできていませんでした。
今回の織田さんの事例で言えば、今の仕事にやりがいを感じられないこととワークライフバランスを取れないこととは織田さんの2つの悩みと捉えており、その両方が重圧となって「この状況から脱したくてもがいている」「やるせない」…ここまで踏み込むことができていませんでした。
杉野さんについては、後輩の転職を機に自身のキャリア発達課題に目覚めて不安になっていると理解していましたが、その根底にある「人との対比により自ら不安を作っている」という洞察には至りませんでした(CL設定はCL役の数だけあることは当然理解したうえで洞察のレベル感を言っています)。
「相談者第一なんて当たり前だろう」と思いながら相談者が本当に苦しんでいることをわかろうとせず、「相談者に存分に語ってもらえた」などと言いながらCCとして聴きたいことばかり掘っていました。残る約2か月、原点に戻って練習していきたいと思います。ありがとうございました。
本気で学びたいと思い、過去に優しく厳しく指導していただいた八阪先生の講座を探しました。
オンラインのよさは、この時先生なら頭で何を考えているかということを、チャットでリアルタイムに知ることができるところでした。
私は話されていることの枝葉末節を完璧に理解しようと、そこに頭を使っていましたが、先生はもう少しそこから離れて、何を訴えているのかに頭を使われていました。もちろん、枝葉末節とは言いましたが尊重しながらです。脳に考える余白をつくるというアドバイスが、完璧主義の私には今回一番重要なメッセージとなりました。わかろうとする努力、幹を知ろうとする関わりができるようになりたいです。
具体的展開まで進むようにかかわってくださいという指示書を渡され、問題は?と問われるので不自然なテスト用の面接をしてしまっていたような気がします。ただまだ自信がありません。練習を重ねたいです。
今回もたくさんの学びと気づきがありました。カウンセリングの奥深さと難しさを改めて感じるとともに、この方向で間違いないと感じており、足りないことばかりの苦しさはありつつも頑張ってやっていこうと考えることが出来ています。以下に学んだこと、気づいたことをまとめます。
①自分のやっていることが、関係構築、問題把握、具体的展開のどれに当てはまるのか、意識しながら進めること。そうすることで、関係構築が不十分なのに具体的展開に飛び込むなど、おかしなことをしていないか、頭の中にイメージできると思う。見学者として聴いている時も同様。
②指導はCCの問題を扱うのであって、話の中心はCCである。持ち込まれた事例は話題でしかない。あくまでも、CCのために何をするべきかを意識し、事例にこだわったり入りこみすぎたりしないように注意する。
③CCが一生懸命に工夫して頑張ったけれども、CLに受け取ってもらえなかったという状況は、私自身もイヤというほど経験している。そのつらさや悲しさを、他人事でなく共感し、労うことによって、CLは癒され、これからも続けていこうという気持ちになれる。
④設定としてSVとCCは初対面なので、「開示していただいてありがとう」「ちょっときついところだろうと思うけれども、聞いて大丈夫?」といった言葉を入れて、CCに最初から無理をさせない配慮をするのは普通の人間関係でもそうであるように当然。
⑤どれだけ関係構築をして、噛み砕いて話しても、SVが指摘したことは、苦い薬であるし、それを咀嚼するには時間が必要。CC側に様々なネガティブな感情が動くのは当然。もしまだ「認めてほしい、分かってほしい」モードであるなら、またしばらく話を聴き、受け止められる状態を作ること。
⑥「丁寧にCLの様子を観察していますね」「CCの苦しい気持ちが伝わってきましたよ」「CLのことを気遣って力になろうとしておられた様子を感じました」「良いポイントに気づいていますね」など、労いや承認の言葉の「在庫」を持っておかないと、とっさの時に出ないなと思った。
一緒に働く仲間が相談者との面談でうまくいかなかったケースについて、自身がしたかったことを語る場面に出くわすことがある。「わたしね、あの人のこういうところが問題だと思って、それを伝えたんよ」「自己PRがきちんと書けてないから、書き直すように言ったんよ」等、相談者の来談がない場合の言い訳をいう。
私がその仲間の話を聞いて、否定しない関わりをしていると、気持ちが落ち着くのか、しばらくして自ら「こうすれば良かった」と言ってくることもあれば、何度も同じくり返しを続けては、言い訳を言ってくることがある。
その時の私の態度や心持ちは、『また、言い訳をしている』とその場でその言い訳を聞いているだけとか、時には、<前にも同じことあったよね>上から目線で、やり方についてアドバイスをすることがある。テキストにある【SV視点の問題点に気づいたら、すぐにその改善に手を付ける指導方法】を実践している。
その視点を踏まえて、実技試験を再考すると、事例相談者(以下、CC)に対して、良かれと思ってやったことを受容・共感しているつもりだったことに気づいた。
CCが事例について語っていただく途中で、自身のやらかしたことや、本当にそれでよかったのかとの思いがあり、葛藤を抱えている状態であり、気づいたからすぐ改善出来るわけでもなく、やってしまったことへの後悔や言い訳等、言いたい気持ちになっていると仮定した。まずは、受容・共感をした後、【SV視点の問題点に気づいたら、すぐにその改善に手を付ける指導方法】を自己中心的に関わり、CCとの信頼関係が危うくなった。
対策講座を受講後に思ったことは、事例指導者がしている基本的態度や関わりを、CCが出会う相談者に対しても同じような関わりをしてしまう可能性があり、その結果、より良い支援に繋がらないんではないか。
場合によっては、キャリアコンサルタントの社会的信用を落としてしまうのではないか。
今回、肝に銘じたことは、日頃から相談者第一に関わることを基本とする、CCの成長を第一に考えて真摯に向き合うことを基本とする。心構えとして【指導とは、CCの成長を第一に考える、そしてCCと共に成長していくこと】を意識する事。
事例指導者としての目標は【一人ひとりが自分らしく、活き活きと生きていけるような社会づくりに貢献したい】と考えた。
今回気がついた私の課題は、「問題を問題として捉えきれていないことを、経験のせいにしていたこと」(考えることを放棄していたこと)です。
相談者が、事例相談者に変わった途端に、問題が見えなくなっている自分がいました。抽象化すると、SVのCCに対する振る舞いは、CCのCLに対する振る舞いと、観念的には同じはずなのに、問題と捉えると、わからない、自信がなくなってしまう自分がいました。
そして、「私はまだ、CCの問題を問題として捉えきれていないから研鑽が必要だ」と、安易に考えそうになっていたのですよね。SVとしての研鑽が足りないのは事実なのですが、誰かから教えてもらうことを待っているという自分がいたことにはっとしました。
ちょっと考えたら、キャリアコンサルタントとしての振る舞いの問題は、まず倫理綱領だったり、能力要件だったりと照らし合わせて考えたらいいことでした。「事例検討の効果的な進め方と倫理綱領の上手な活用法」の更新講習でも学習したのに、1級の試験と身構えて、さらに、「まだ経験が・・・」と言って逃げそうになっている自分がいたんですよね。
確かに、今回の1級の講座では、八阪先生の視点が3事例分見られてとてもとても嬉しいのですが、先生の視点がもらえるからと、受講時点で自分が自分で考えるというマインドを、最初から捨てちゃってたなと反省しました。
これは、普段から、倫理綱領や能力要件を空気のように理解している必要があるかもと思いました。倫理綱領は面談前に読むようにしていましたが、能力要件も読む機会を増やそうと思います。そのうえで、指導の場面で、どのように対話するかは、コミュニケーション、関係構築のスキルを上げることだと感じました。
ここは今回は、
– 面談の中の事例相談者の様子そのものが、そのまま指導の材料になること。
– 事例相談者が意図を持ってやろうとしたことを、そのまま確認することで、意味付けを行うこと。
– 事例相談者の振る舞いに対する矛盾をしっかり考えられるようになること
などの気付きもありましたので、実践でトライしたいと思います。開催ありがとうございました。
ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。
できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、
今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。
当日の講座の様子
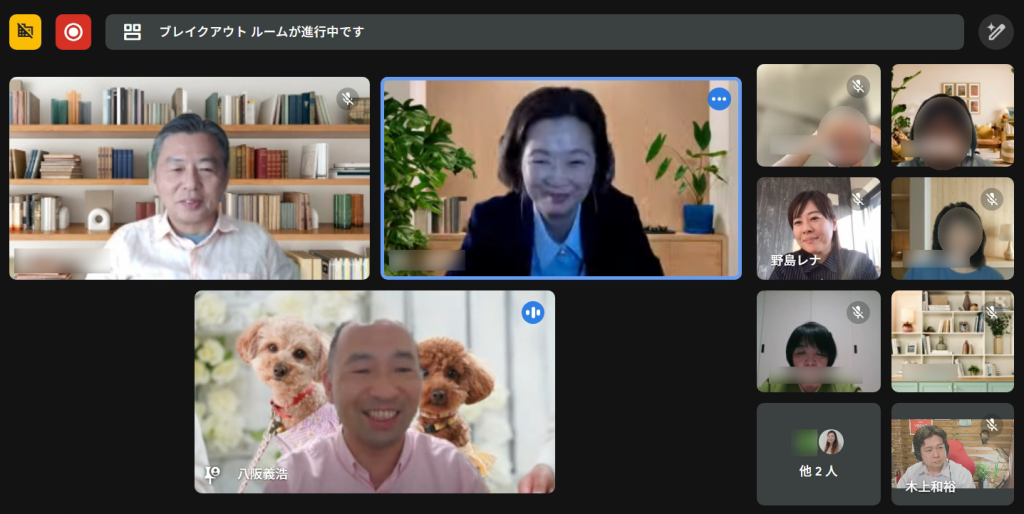
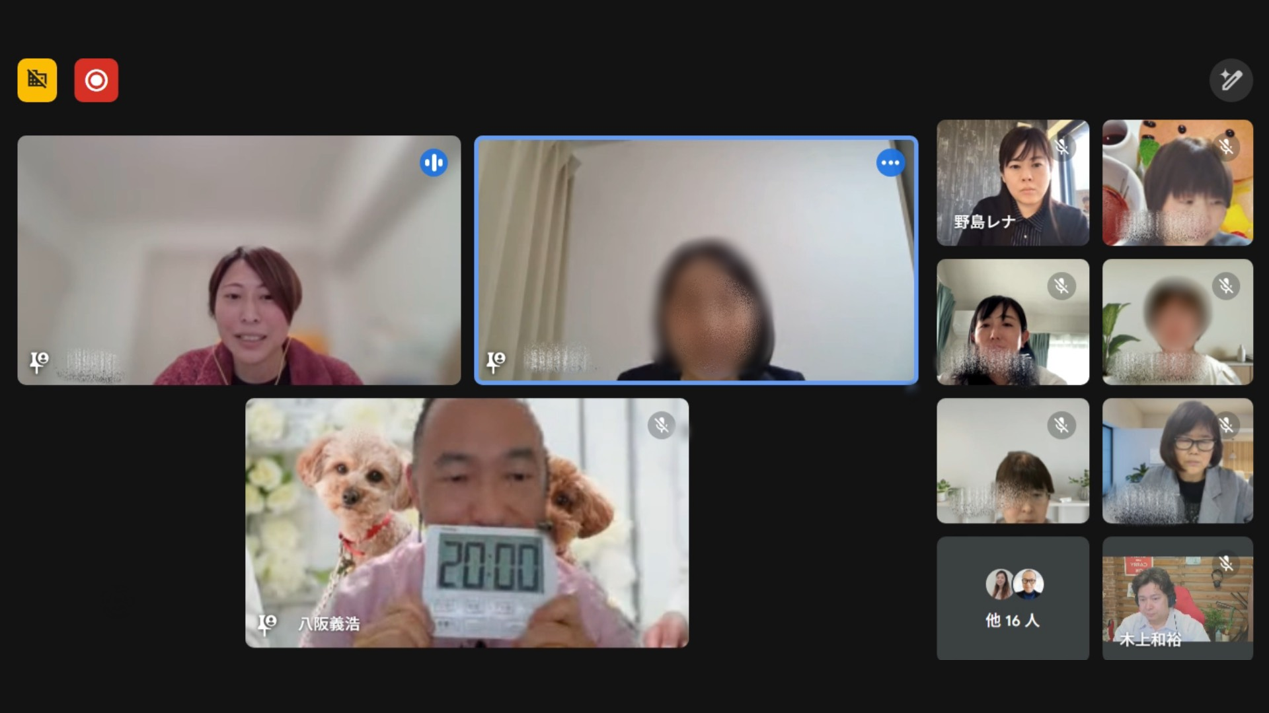


アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。
まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。
いい感じでスマイルになっているところを切り抜きたくて、
サポーターのお二人が奮闘してくださったので
真剣な中にも楽しく学んでいただける、弊社ならではの雰囲気は伝わるでしょうか?
おそらくフィードバックの時にちょっとした「ツッコミ」を
入れているシーンだと思いますが、堅いばかりだとしんどくなるので、
講座の中では、場がほぐれるようなお話も随所に入れていくようにしています。
そんな雰囲気の良さ・学びの場の温かさと、CCとして成長していくための真剣な内容と、
楽しさと厳しさを両立できるようにお話をさせてもらっているので、
そういう場が良いな、体験してみたいなと思ってくださった方は、
ぜひ、弊社の講座で一緒に学んでいきましょう。
それでは、今回はこのあたりで。また次の講座でお会いしましょう。
2025年度の1・2級CC技能検定対策講座のご案内
弊社が企画・運営するキャリアコンサルティング技能検定対策講座について、
弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを
わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。
特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。
「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、
絶対外せない大事な視点や、指導者レベル(1級)・熟練レベル(2級)にふさわしい考え方や姿勢を
きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。
初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、
何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、
揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。
次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や
「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、
しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。
2024年8月からはオンラインストアでの動画販売も始めましたので、
講座での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。
講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、
それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。
※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。
表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。
その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。
みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。
ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。