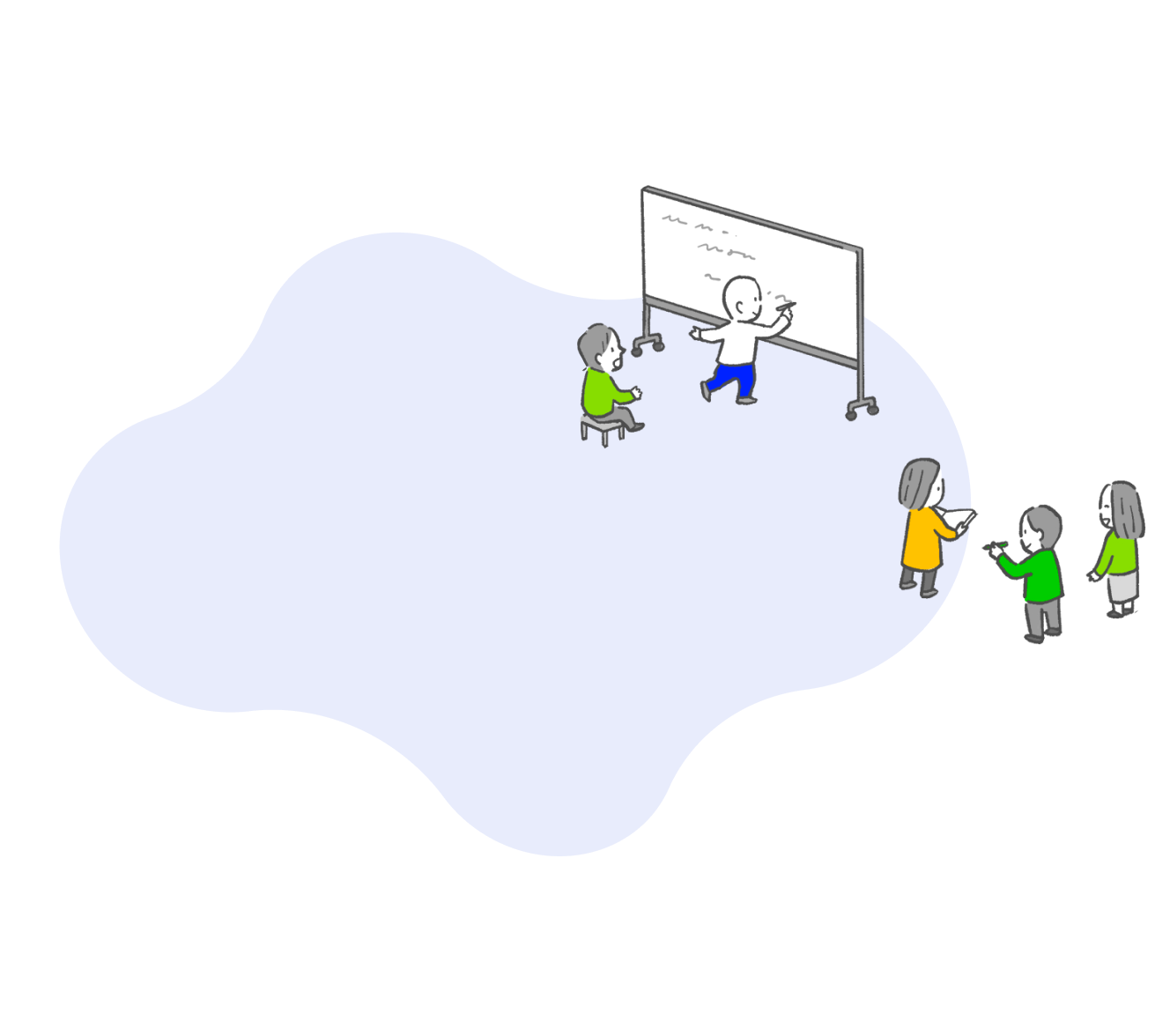11/2(日)にGoogle meetを用いたオンライン形式で
「2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座」
~面接実践編オリジナルコース・口頭試問編~
を開催いたしました。
こんにちは。働く楽しさ研究所・サポーターの内田です。
秋の三連休の中日、午前は「2級面接実践編オリジナルコース」、
午後は「2級口頭試問編」とダブルヘッダーでの開催となりました。
午前の「2級面接実践編オリジナルコース」には13名の方が参加され、
初めてロールプレイに挑戦された方もいらっしゃいました。
参加者のみなさまが、自身の課題、必要な学びを、練習の場を上手に活用して
吸収しようとしてくださっていたのが印象的でした。
講師の言葉にもあったように、2級の課題に簡単なものはありません。
どの課題も深く、そして時に「どこが主訴なのか」が見えにくくなる要素を多く含んでいます。
相談者の訴えを聴きながら、枝葉に迷い込まず幹(本質)をとらえていく。
「相談者が言ったこと」はあくまで「考えの一部」であり、
「相談者が本当に訴えたいこと」と「相談者の言葉」は必ずしも一致しない、
という学びが印象に残りました。
午後の「2級口頭試問編」には4名の方が参加され、
熱心かつ温かなディスカッションが繰り広げられました。
この講座では、1つのロールプレイをもとに、まず個人で回答を考え、
その後、より良い回答を導くために参加者全員で検討します。
ディスカッション中には、「そんな見方もあったのか」と、
参加者同士で新たな気づきを得る場面も多々ありました。
話し合いが進むにつれて、参加者が主体的に意見を交わすようになり、
最後には、相談者の気持ちをまるで自分のことのように受け止め、
静かにその思いを味わうという貴重な瞬間が生まれていました。
CCが自身の考える方向へ面談やCLの人生を導くのではなく、
あくまでCLの立場に寄り添う関わりを意識することの大切さを、改めて感じさせられました。
それでは、ここからは講座の中でも要点になった箇所を振り返ってみましょう。
講座内容の振り返りは、stand.fmによる音声配信形式にてお届けしています。
ブログのように文章を読むのとはちょっと違った形式ですが
「ながら聴き」ができること、視覚を奪われないことなど、
音声ならではのメリットがありますので、そこを上手に活用して復習してください。
「2級 面接実践編オリジナルコース」の振り返り
「2級 口頭試問編」の振り返り
では、ここからは、今回の講座にご参加いただいた方のアンケート内容をご紹介します。
受講された方の意欲や熱意は、アンケートを通してわたしも1人1人丁寧に確認しています。
今回の学びの内容をどれくらいの熱量で発信していけるのか、
考えを整理し・言語化する訓練と捉えている人と、
ただの回答だと思って適当に済ませる人とでは、頭の鍛えられ方が全然変わってきます。
いつもお伝えしていることですが、本気で2級合格を目指すのであれば、
上位15%に入るアウトプットをしようと、こだわって回答してくださるはずですね。
熱意ある受講者さんがどれくらいのものか、ぜひこの回答から感じ取ってください。
2級 面接実践編・口頭試問編 参加者の声
コスパの良さにいつも感動しています。面談内容の解説、最後の自由質問、講座後に届くポイントも含め、本物を目指して欲しいという思いが伝わってくる惜しげもない講座内容に、本物の支援者には程遠い自分自身の未熟さを感じながらも、感銘を受け日常の会話さえも八阪先生の考え方に寄ってきている自分を感じています。
・クライアントの言葉や態度から本当の思いをくみ取ることが難しく、つい表面的な問題解決に走ってしまいます。八阪先生のような視点を少しでも身に付けたく、質問をさせていただいたところ、「日常の中にも相手の気持ちを汲み取る場面は多くある」というヒントをいただき、日常でも相手の言葉だけでなく、その裏にある言語化されていないメッセージを受け取る機会はたくさんあることや、「営業になってしまった」といったような一つの発言の端々からも、相手の感じていることを汲み取ることができると気づきました。
また、一般論を使って想像することの大切さも学びました。単に「一般的に考えて無理だよね」と捉えるのではなく、一般論を手がかりにクライアントの気持ちを想像し、それを言語化していくことが重要なのだと感じました。
・頭の中の整理については、こんなのは自分だけなのでは?と思っていたので、質問しづらい内容だったのですが、他の方が質問してくださり、具体的な対策をていねいに教えていただけました。まずは何が頭に残っているか書き出してみることで、残っているものが幹なのか枝葉なのか判断する。ペースをゆっくりにする。自分の理解できる間をつくる。これであってますかと途中で確認をいれて丁寧におさえていくなど・・・早速やってみようと思います。
本日はたくさんの具体的なヒントをいただいたので、実践し、続けていきたいと思います。有意義なお時間をありがとうございました。
今回、講座で初めてロールプレイをさせていただきましたが、課題である「CLの気持ちの受け止めが弱く、伝え返せない」点を意識しました。動画を見直しましたが、伝え返せないどころか、そもそも気持ちを汲み取ることもできていませんでした。あるシーンでは受け止めずに追加質問をし、ある程度理解ができた時点で共感的な言葉を伝えましたが、最初の時点でも一旦は軽く受け止めたほうが良かった、と感じました。
今回の事例は開始時、どのような言葉をかければよいのかとても難しかったのですが、関係構築を意図して丁寧に関わったことは良かったようです。一方、口頭試問の「CC視点の問題」に答えることができませんでした。八阪先生からは面談の設計(=見立て=見通し)ができていれば、口頭試問がもっと楽になるとのご指摘をいただきました。さらに脳の使い方を工夫すれば、弱点だと思っていた記憶力の悪さを克服できるだけでなく、様々な恩恵に預かれそうだと期待が出てきました
私は普段からよくメモをしますが、実務でもなぐり書きのメモをします。しかし、2級受験はメモ禁止ですから、聴いた内容をどう整理すればよいのかが悩みの種でした。これまで個別指導でのロールプレイや自主練習では目の前のCLに集中し、口頭試問では記憶に残っているキーワードをかき集めて答えるため、まとまりのない回答になります。今回のロールプレイでは、CC視点の問題が答えられないという残念な結果となりました。
今回の講座では、すべてを覚えるのは不可能なため、CCに求められる「CLが訴えていること」を把握できればよい、と割り切る大切さを学びました。CLの話の「幹」と「枝葉」を切り分け、CLが「枝葉」を話している時こそ考えるチャンスなのだ、と。こうして考える時間が確保できれば、面談の設計(=見立て=見通し)をすることもでき、口頭試問も答えやすくなるのだ、と。
しかし重要で忘れてはいけないのは汲み取る力です。私の場合は、状況理解に関心が向かってしまうため、CLが話したいこと、聴いて欲しいことを「幹」としてしっかり意識することを初めの一歩として取り組みたいと思います。この頭の使い方はすぐにできるわけではないかもしれません。だからこそ、回数をこなして慣れていきたいと思います。
今回、3事例を見学させていただき、2級面接試験がいかに難しいかを再確認させていただきました。八阪先生も講座中に何度か、面接試験で優しいケースはないとおっしゃっていました・・3事例に共通して感じたことであり、学ばせていただいたのは「相談者の話の聴き方、汲み取り方」「面談コントロール」になります。
<1つ目のケース>では、相談者の言いたいこと、話したいことを聴くことも方策だと学びました。但しそれを選択肢した意図・根拠が必要になる。CLさんは、仕事をしている時はゆっくりしたい、ゆっくりしていると仕事をしたいと反対側に影響される、引っ張られる思考の傾向があり、CCの見立てとして関わりたいと感じました。
<2つ目のケース>では、死生観に関わるデリケートで扱いが難しい話題の取り扱いでした。「話したくないことは、無理に話さなくていいですよ」の一言が大事。相談者の情報量が多い話題の、何が幹で何が枝葉なのか、相談者が訴えたいことは何かを拾えるように面談をコントロール、見通しを持つことが大事だと感じました。
<3つ目のケース>では、来談経緯と主訴は違うと言うこと、未来は暗いと思って来談された相談者は何を汲み取って欲しいのかを考えて関わることが大事だと感じました。
表面的に相談者の話を聞くのではなく、何故相談にこられたのか、何故立ち止まって行動できないのか、話の仕方や言い回しから汲み取れるように意識して面談に臨みたいと思いました。
口頭試問の答え方を学ぶ会でしたが、それと同時に面談で意図を持ったお話の伺い方ができていないと口頭試問で何も答えられないということがよくわかりました。
それを深く感じたのは、他の方が行った面談をもとに、発言→意図→結果→評価の順に答える内容を一つひとつ皆さんと紐解きながら考えましたが、意図を考えることの難しさを感じました。これを通じて、どういう意図を持ってCLの言葉を自分が感じたこととして伝え返したのか、どういう意図を持って質問をしたのかそれがあるからこそ、CLのその後の反応や話の内容がこうなった、だからこそ出来たことや出来なかったこと、関係構築をどのように深めたからどうなったと答えることができると思いましたし、だからこそ、問題点の把握や今度の展開をそのCLに沿った内容を考えることができると改めて理解しました。
これは自身の面談後も大切な作業だと思いました。口頭試問ではその場で答えられるのも意図を持った面談ができているからであって、それができるためというよりも、自身の面談後も口頭試問の内容を一つ一つ振り返ることが、面談の質がよりCLが求めるものに近づくんだなと感じました。
また、できなかったところを「〜の話をもっと早く聞けばよかった」はおかしいと教えていただきました。まさに今までの自分で、時間内に聞けなかったことは口頭試問で「〜を聞くことができませんでした」と言えばいいと思っていましたので猛省です。先生の仰る通り、これでは聞くのが正しい、CL第一から外れていると思いました。また、結果と根拠をごっちゃにしないについても、まさに今まで、そのように答えていました。これも全て意図がないCL第一の面談ができていないから出てきた答えでした。
早速、教えていただいたことをもとに、口頭試問の内容をまとめてみました。これをロープレをするたびに続けて行きたいと思います。
CL視点を徹底した面談というのが頭で理解できても、それを実技面談でCCとしてCLを前にしてできるあどうかの間には思った以上の違いがあることを改めて認識しました。
関係構築の際には、CLに肯定的関心を持って、CLの気持ちを傾聴していく。特に相手のマイナス感情を聞いていく。あくまでCLが話したいこと、吐き出したいことを語ってもらう。その会話を通じて、CLの「認知の変化」が起こるような内省を促す。その語ってもらった中で、最もマイナス感情が現れていたところがCLの主訴であることをCCとCLで確認し合う。
例えば「以前の仕事を天職と考え、使命感を持ち、生きがいを持って取り組んできた仕事、それが異動により営業になってしまいできなくなり、どうしたら良いかわからない」ということが面談の前半のもっと大きなマイナス感情だと思う。その際には、CCとして捉えたCLの問題が何かを一歩引いた視点から把握していくことが重要である。
しかし、実際のロープレでは、この主訴とCCとして捉えたCLの問題をしっかり分けて把握すことが予想以上に難しいことも改めて認識した。例えば、CLが「以前の仕事をしている自分の姿しか考えられず、異動になり天職として使命感を持っていた仕事ができなくなってしまったことを、未だに受け止められずにいる。上司に相談しても営業に異動して半年なのだからもっと頑張ってみろと言われることがわかっているから相談もできない」はその典型的事例である。
CL視点に立った場合、この問題認識を理解したうえで、今後の展開をどうしていくのか。今のCLの「未だに受け止められずにいる」気持ちにしっかり寄り添ったうえで、では現状を受け止めた上で、どのような働き方があり姿なのか決めることを目標とする。それをCLと一緒に検討する。あくまでCLが自ら意思決定し、前向きに行動できるように支援していく。以上が今回のロープレで気づいたことです。
ここに掲載されていなくてもすごくいいメッセージを書いてくださっている方はまだまだたくさんいます。
できるだけ”多様な視点”になることを意識して掲載する文章を選んでいますので、
今回ここに掲載されなかったからと言って、ガッカリしないでください。
当日の講座の様子




アンケートにご協力をいただいたみなさま、ありがとうございます。
まだの方も、よろしければぜひご感想をお聞かせください。
口頭試問では、面談中の「発言」「意図」「結果」を踏まえて「評価」することが求められます。
これは、熟練レベルのCCに必要とされる姿勢や技能の証であり、
面談の中での「見えない意図」を自らの言葉で説明できる貴重な機会でもあります。
また、その意図が「誰のためのものなのか」を見失わないようにしたいですね。
午前・午後の両方にご参加くださった方もおり、長時間にわたり本当にお疲れさまでした。
今回の学びが、試験対策にとどまらず、日々の面談や相談者理解の深まりにつながることを願っています。
それでは、今回はこのあたりで。
また次の講座でお会いしましょう。
2025年度の2級CC技能検定対策講座のご案内
弊社が企画・運営する2級キャリアコンサルティング技能検定対策講座について、
弊社ならではの特長やメリット、お客様の声、よくある質問(Q&A)などを
わかりやすくまとめたページをご用意いたしました。
特に、弊社では「面接準備編」の講座の受講から始められることをお勧めしています。
「面接準備編」では、最難関とされる実技試験(面接)の突破に向けて、
絶対外せない大事な視点や、熟練レベル(2級)にふさわしい考え方や姿勢を
きちんと身に付けることを目的として企画・設計している内容です。
初めて試験にチャレンジされる方はもちろん、
何度挑戦してもなかなかうまくいかない方にとっても、
揺るがない足場を整え、困った時の拠り所がわかる内容です。
次の試験で合格したい!という方は、いきなり「面接指導編(ロールプレイ講座)」や
「事例読み解き編」などの実践編から入るのではなく、
しっかり基礎固めができる「面接準備編」から一歩ずつ学んでいってほしいです。
一部の講座は、オンラインストアでの動画販売もしておりますので、
講座形式での参加でも、動画形式でも、学びやすい方法をお選びください。
講座で参加されたい方と、オンラインストアの動画講座を購入して学びたい方、
それぞれに合わせてリンク先のボタンを下の方に用意しています。
※講座の場合、クリックすると開催日程カレンダーが表示されます。
表示されたページの中から、希望の日程をクリックしてください。
その後、詳細な内容などがご覧いただけるようになります。
みなさまの指導・支援ができる機会を心待ちにしております。
ぜひこの機会に弊社講座にお越しくださいませ。